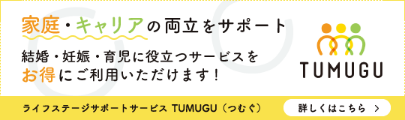男性育休、制度は整ったが入り口に立ったばかり。鈴木 啓人さんが語る現実と課題
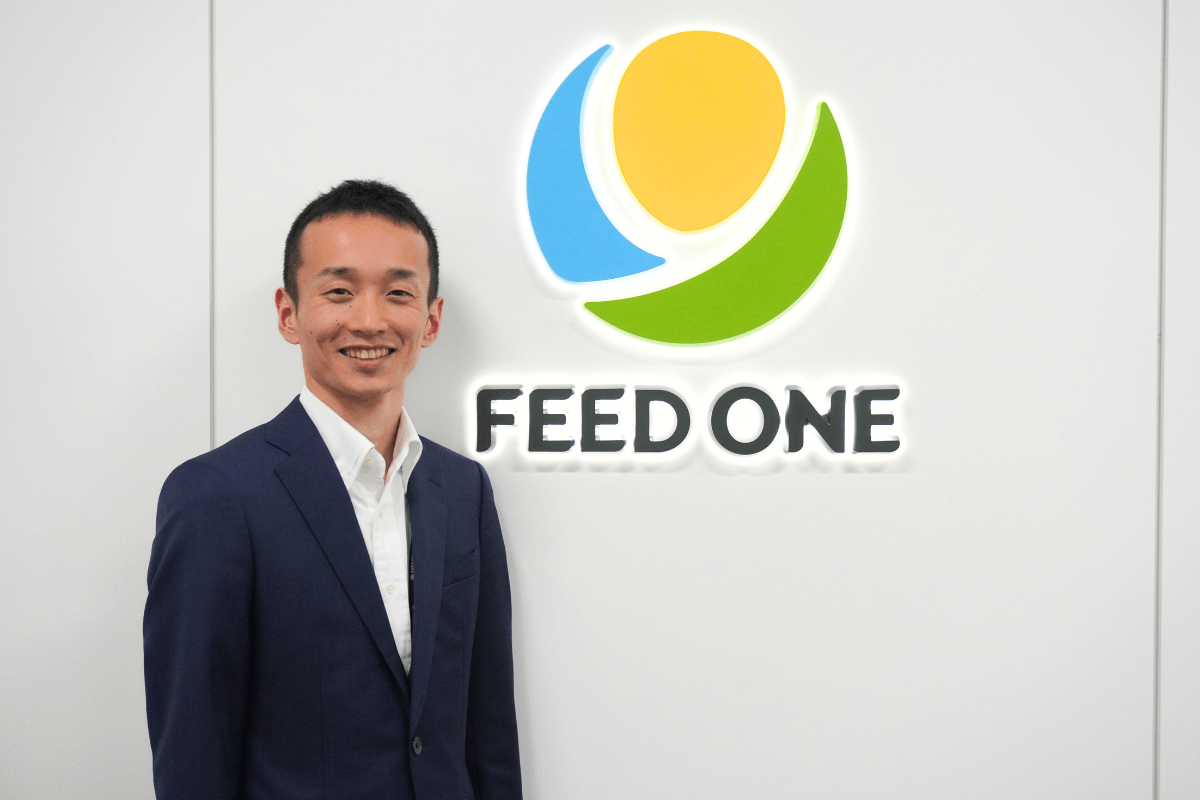
2024年、男性育休取得率が初めて3割を突破しました。(※1)「育児・介護休業法」の法改正の影響もあり、職場で育休を「取りやすい」環境が少しずつ整いつつあります。2025年には、育児休業取得状況の公表義務が拡大し、さらに多くの企業が、男性の育休取得率向上を目指す取り組みを求められるようになります。(※2)それでも、現場では環境や慣習が“壁”となることも多く、取得後の働き方に悩むケースが少なくありません。
配合飼料の大手、フィード・ワン株式会社で新卒採用を担当し、自らも育休を取得した鈴木啓人さんは、「育休を取るのは第一歩。その後どう向き合うかが大事」と語ります。鈴木さんの体験から見えてきた、男性育休のリアルな課題と可能性を考えます。
「実際に取ってみてどうだったのか?」「上司やチームメンバーはどう対応したのか?」「会社としてどんな制度で後押ししているのか?」など、育休取得を考える男性や、制度設計に関わる企業担当者に向けて、ヒントとなるメッセージをお届けします!
(2024年9月取材)
(※1)男性の育児休業取得率30% 過去最高 厚労省の調査(NHK)https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240731/k10014531051000.html
(※2)リーフレット「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内令和7(2025)年4月1日から段階的に施行」(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
目次
インタビュー参加者プロフィール
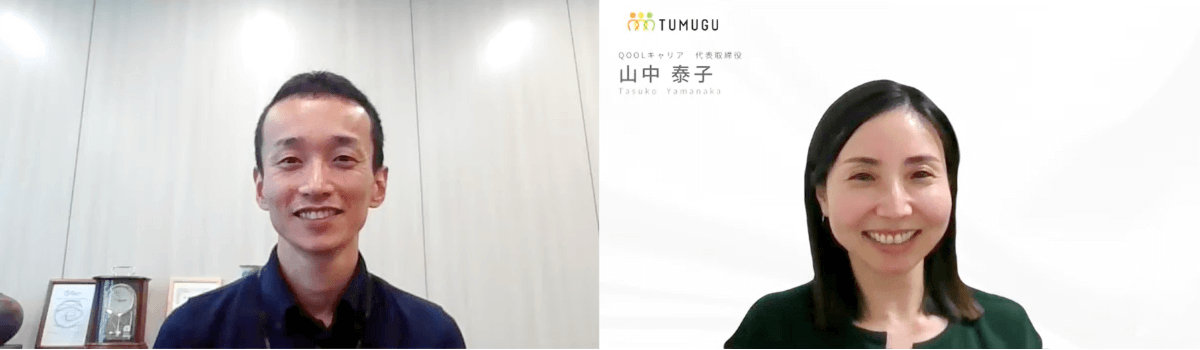
鈴木 啓人(すずき ひろと)さん(写真左)
フィード・ワン株式会社 人事部 係長
大学卒業後、2012年にフィード・ワン株式会社(以下、フィード・ワン)に新卒入社。2年間水産飼料の営業職に従事した後、2014年に当時としては異例のキャリアチェンジで財務経理部に転属。同じ年に同業他社との合併を経て、会社の体制が大きく変わる中、財務経理部で8年間の経験を積む。2022年に人事部に異動し、新卒採用を経験した後、2024年9月からは人事企画業務を担当。2023年には1ヶ月間の育児休業の取得等、4歳と2歳の父として両立に奮闘している。
今回のインタビューは鈴木さんのお話を中心にしつつ、会社の制度面については、
高旗 由加里さん(人事部)、小泉 千夏さん、花輪 真未さん(経営企画部)にもご協力いただきました。
山中 泰子(やまなか やすこ)(インタビュアー)(写真右)
株式会社QOOLキャリア 代表取締役社長
大手IT系人材サービス企業で人事として、採用・育成・制度設計等を経験。自治体とともにひとり親家庭の就業支援事業を立ち上げ、保育施設を併設した就業施設の開設・運営に携わる。その後、上場会社の人事担当執行役員、スタートアップ企業の人事責任者を経て、2022年4月からQOOLキャリアで代表に就任。1児の母である自らの経験も活かし、キャリアアドバイザーとして仕事と育児の両立に悩む女性のキャリア支援も行う。
育休取得を決断した理由
――育児休業期間と取得の時期はどのように決めたのでしょうか。
鈴木さん(以下、敬称略)
1人目の時は育休を取りませんでしたが、2人目の時は家族のサポートをしっかりしたいと思い、妻とも相談して時期を決めました。妻は、里帰り出産だったので、特に、里帰りから戻ってきてからの協力が必要だと感じていました。また、その時期は生後8か月になる頃なので、動きが活発になることもあり、サポートが欠かせないと話していましたね。仕事のスケジュールとも照らし合わせ、比較的落ち着いている1か月を取得期間に決めました。今振り返ると、生まれてすぐのタイミングでも2回に分けて育休を取っておけば良かったかな、と思うこともありますね。
――実際に育休を取られていかがでしたか?
鈴木
短い期間ではありましたが、子どもの成長が間近で見られ、家族と過ごす時間が取れたのは貴重な経験でした。特に2歳年上の長男との時間を持つことができたのはとても良かったと感じています。育児以外にも家事など、母親以外にできる役割がないかを探しながら積極的に担当してきました。育児というと、母親が中心と思われがちですが、実際には父親もできることはたくさんあります。この期間子どもとの接し方をはじめ、改めて育児の大変さを体感しました。子どもから学ぶことも多かったですし、自分も家族の一員としてしっかりサポートできたと思ってもらえていたら嬉しいですね。
山中
私も子育て中ですが、1人でも大変なので、2人となると本当にサポートが欠かせないなという雰囲気が伝わります。そんな育休期間を経て、今はどのように育児に関わっていますか?
鈴木
今でも保育園の送迎や行事への参加、家事や育児に積極的に関わっています。
平日は、妻が時短勤務なので、17時に子どもを迎えに行き、その後はおやつ→お風呂→夕飯→寝かしつけと私も参加しながら、バタバタと動き回っています。子どもの睡眠時間を確保するため、スケジュールが後ろ倒しにならないように気を付けていますが、22時頃には正直ヘトヘトで記憶が曖昧になることもありますね(笑)。
先日、保育園の行事で半日間の保育士体験にも参加しましたが、他の父親も積極的に育児に関わっている様子を目の当たりにし、とても刺激を受けました。これからも、子どもと一緒に成長していきたいと思います。
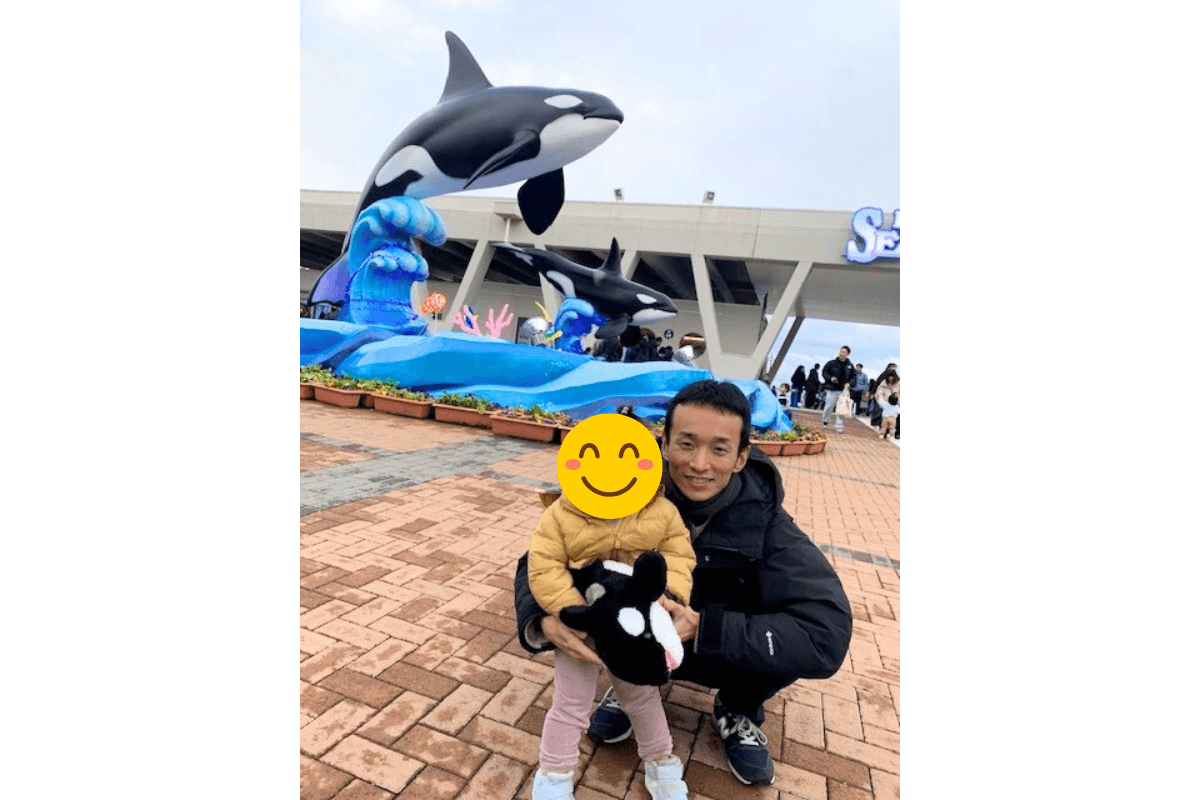
本当の大変さは「育休中」より「復帰後」にあった
――お子さまが生まれると分かったとき、まずどんなアクションを取られましたか?
鈴木
上司や後輩、育休関係の窓口となる担当者に連絡を取りました。その後、里帰り出産のタイミングを考慮し、育休の取得時期を調整しました。育休だからといって新たに大規模な引き継ぎが必要だったわけではなく、普段から業務を共有しながら進めていたため、スムーズに育休に入れました。上司も周囲のメンバーに積極的に声をかけてくれ、チームからサポートを得られたことは本当にありがたかったです。
――育児に集中する期間を経て、復帰してからの働き方にはどのような変化がありましたか?
鈴木
育休を終えてからのほうが、むしろ突発的な休みへの対応が難しいと感じる場面が増えました。子どもの急な体調不良などで「どちらが迎えに行くか」や「明日休めるか」といった細かい調整が日常的に発生するんですよね。育休を機に、現物(紙資料など)を管理しないことや、業務のデジタル化を意識し準備してきたので、引き継ぎのしやすさは各段に上がりました。

山中
育休がきっかけとなって、誰でも対応できる体制を整えられたのは大きな成果ですね。復帰後、突然子どもの病院などで休む必要があっても、育休中に築いた仕組みが延長線上で活かされる。これは素晴らしいですね。
育休から明けて10か月程立ちますが、在宅勤務は週に何回と決めて利用しているんですか?
鈴木
特段決めてはなく月に数回程度で、出社を多くしていますね。後輩の引き継ぎだったり、社内のコミュニケーションだったり、今は出社のメリットが大きいかなと思います。
日常的にランチの際など、お互いに「子育て大変だね」といった会話を通して、自分だけがしんどいわけじゃないんだな、と思えることも出社への意欲になっています。
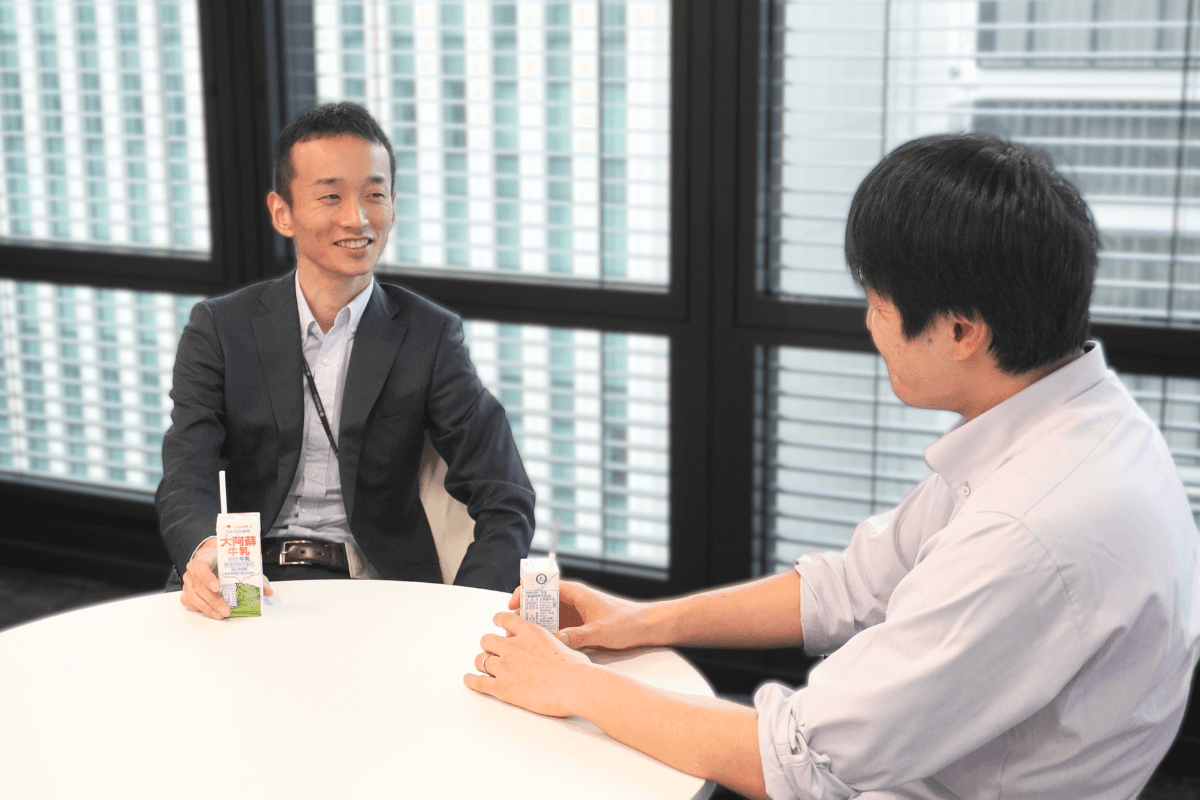
山中
普段から自分の置かれている状況を周囲に伝えていると、お互いの状況理解が深まって、ヘルプもしやすくなるのがとてもいいですね。
鈴木
育休を取ったことで、「子育て中だ」という状況が周囲に浸透したのも働きやすさに繋がっています。一方で、復帰後の大変さは、突発的な休みや対応にかかる時間が数値化されにくく、会社としても課題を明確にしづらい部分があると感じています。
それでも、育休取得をきっかけに進めた業務のデジタル化や情報共有の体制づくりが、急な予定の変更に役立つ場面が増えてきました。こうした仕組みが整備されることで、想定外の事態が発生しても職場全体でフォローできる体制が生まれ、働く全員にとっての安心感に繋がると感じています。
人事担当者だから気づいた、育休取得のリアルな課題
――仕事と家庭の両立を後押ししてくれている会社の制度を教えてください。
鈴木
妻の妊娠報告の際に、育休が分割して取得できることや自治体との連携など、多くの制度について知ることができました。復帰後は、時間有休制度と在宅勤務制度を主に活用しています。保育園の送迎など子どもとの時間に使えるため、非常に助かっています。
制度が整っているのはもちろんですが、何より周囲の理解とサポートが大きな支えになっていますね。
花輪さん(以下、敬称略)
個人面談以外にも育休関連の法改正がある度に社内全体へ情報を周知しています。「子が1歳までの間に分割して2回取得できるようになること」や「出生時育児休業(産後パパ育休)」についても伝えていましたね。
鈴木
ただ、職種によって環境が大きく異なるのも事実です。事務職では制度を活用しやすい一方で、営業職では移動や宿泊出張が多く、同じように活用しながら働くのが難しいこともあると感じています。
――全社員の育休を取りやすくするために、なにか取り組んでいることはありますか?
小泉さん
男性の育休取得率が高くないことに課題認識があったため、管理職の意識を変えることを目的として「マイキャリアデザイン研修」を取り入れました。管理職と育児等のライフイベントを経験した30歳前後の女性社員が意見交換を通じて、仕事と家庭の両立や価値観の違いを学ぶ場を設けています。内容としては、育児や親の介護、女性社員が抱える健康課題や、ホルモンバランス、更年期についてなど、幅広いトピックが取り上げられます。また、新卒の学生がどのような考え方で入社してくるのかも学びます。入社時の期待や定着のための方法についてのレクチャーもあり、働き方や価値観を見直す良い機会となっています。
高旗さん
制度の整備に10年取り組んでいても、「取りづらい」「活用しにくい」という現場の課題はまだまだあります。文化や風土の醸成には時間がかかりましたが、制度を整えていくことで、今ようやく歯車が動き始めたという感覚です。まずは鈴木をはじめとしたロールモデルとなる男性社員を増やし、男性の育休取得が当たり前の環境を目指しています。
花輪
全社員必須のeラーニングで育児や介護、ダイバーシティの研修を実施し、受講率は100%です。年間10項目ほどの研修を通じて、その時に必要な情報を取り入れ、風土の醸成に繋がればと思います。

鈴木
研修や制度は十分に整っていますが、それを現場で活かすためには時間がかかると思います。自分の経験を伝えることで、次の世代に少しでも役立つ文化を作っていきたいです。
山中
育休取得の事例が増えることが、社員一人ひとりの意識や環境を変える鍵になりますね。これから入社される新卒の方は大学生時代からキャリアの勉強をしていて、就活でも、家庭と仕事の両立を意識しながら企業を選択していく世代なので、データなどでもしっかり発信されていて素晴らしいですね。
データで見るFEED ONE:https://www.feed-one.co.jp/recruit/data.html
後輩を育てるキッカケにもなった育休取得
――育休を取得して、周りの反応はいかがでしたか?
鈴木
育休を取ることが「当たり前」だと感じる人が増えています。私自身、最初は罪悪感や社会から置いて行かれる不安がありましたが、今では他の社員も育休を取りやすくなったと感じています。
不在中は負担をかけてしまいましたが、その経験が新たなスキルとなって成長に繋がった後輩もいました。実際に個人的な経験でも、上司が抜けた時にチームが自主的に業務を調整しながら対応した経験が、意外と役立つこともありました。特に財務経理部時代、少し負担がかかってもチーム全体で頑張ることが次のスキルに繋がったんです。部下や後輩だからと守りすぎるより、あえて任せてみることで見えてくる成長もあると実感しましたね。

山中
私も産休・育休を取得した際、キャリアが終わるかもと感じることがありました。実際、時短勤務で仕事の量が減り、物理的にできなくなったことも多かったです。しかし振り返ると、その経験を通じて学べたことが多く、良い転機だったと感じています。無理にでも転機を作ることで、新たに気づけたことが多かったんですよね。
鈴木
育休を取ることは、自分自身の成長だけでなく、後輩たちに新たなチャンスを渡すことにもなると思います。現場ごとにロールモデルを増やしていくことが今後の課題です。
新卒採用の現場では「これまでのキャリアパスはどうでしたか?」「どんなキャリアパスがありますか?」と質問されることがよくあります。その時は、実際の経験を正直に伝えるようにしています。働き出すと価値観は変わるものなので、すべてを決めつける必要はないし、何でも話せる職場環境があれば、後々どうにかなるという私の想いを合わせて伝えています。
育休を迷うすべての方へ
初めての育休取得は、きっと勇気がいることだと思います。でも、「会社に迷惑がかかる」という気持ちは少し脇に置いてみてください。実際に取得してみると、周りの意識が変わり、その時に作った仕組みが後輩やチームの働き方に役立つことも多いんです。育休中にチームがカバーし合うことで、スキルアップした後輩もいました。そんな前向きな変化を目の当たりにすると、「育休を取って良かった」と実感すると思います。
仕事と家庭の両立を図ることは、その姿を見ていた社員にとって将来の働きやすさにも繋がることと思います。育休が終わって保育園の登園が始まると、日々の送迎や看病の対応などで、育休の時以上に多忙な日々が続きますが、それもまた大切な時期です。そんな中でも社内で支え合える雰囲気を作ることが重要だと感じています。
私自身子どもの熱が出た日は早めに帰ったり、時間休をフル活用して送迎したり、周囲の支えでできることが増えました。
もちろん育休を取得したら育児を頑張ってくださいね!
最初は不安かもしれませんが、やってみたら想像以上に得られるものがきっとあります。自分のペースで、一歩踏み出してみてください!

編集後記:鈴木さんの想いを振り返って
今回の取材を通して感じたのは、個人としても会社としても前に進もうとする鈴木さんの姿勢でした。現場ごとに課題の温度差はあるものの、それを真摯に受け止め、改善に向けた一歩を踏み出そうとする姿に深い感銘を受けました。
育休をきっかけに、業務のデジタル化や情報共有の仕組みづくりに取り組み、復帰後の働きやすさに繋がる成果を積み上げていく姿は、誰もが安心して働ける職場環境づくりへの道筋を示しているように感じます。
誰かが思いを持ってアクションを起こさないと変わっていかない難しい課題ですが、フィード・ワンにはその想いがしっかりとあり、一人ひとりの取り組みが力強い原動力となっていることを実感しました。
鈴木さんの経験と言葉は、多くの方にとって励みになるはずです。今後もその想いがさらに広がり、職場や社会に変化をもたらす一助となることを心から願っています。
フィード・ワン、日本の食を根底から支える企業のご紹介
皆様が毎日食べている卵・肉・魚・乳製品の生産には「配合飼料」が密接に関わっていることをご存じですか?
フィード・ワンは、家畜や養殖魚の餌となる配合飼料の製造・販売を行っています。また、飼料事業だけでなく食品事業も手掛けており、食の川上から川下まで一貫した事業を展開しています。普段の生活では身近に感じることが少ないですが、食卓を彩る畜水産物の生産を支え、家畜や養殖魚の命を支える仕事にやりがいを感じる職場です。
企業成長の源泉は人材であると考え、働きやすい職場環境の整備と社員一人ひとりの生活や働き方に柔軟に対応できる人事制度や福利厚生の充実に努めています。詳しくは会社HPをご覧ください。
HPはこちら:https://www.feed-one.co.jp/
男性育休取得をサポートする福利厚生サービス「TUMUGU(ツムグ)」
QOOLキャリアは、すべての人が「私らしく働く」ことができる社会を実現するため、企業と従業員の成長を支援する様々なサービスを提供しています。男性の育児休暇取得を推進する企業向けに、福利厚生サービス「TUMUGU(ツムグ)」をご紹介します。
TUMUGUは、育児休業の取得をサポートし、家庭と仕事を両立できる環境づくりを支援します。育児休暇を取得しやすくするための仕組みや、社員がライフステージに合わせて柔軟に働けるサポートを提供。企業の成長と従業員のワークライフバランスを両立させ、長期的な活躍を促進します。
TUMUGUのサービスサイトはこちら:https://tumugu-service.jp/
お問い合わせはこちら:https://career.qo-ol.jp/tumugu/