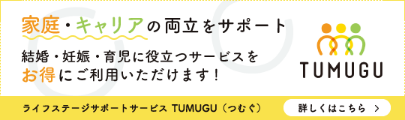毎月の悩みから生まれた『職場のロリエ』―理想のワークファミリーバランスを実現する手島佑梨さんと松永沙都子さんの挑戦
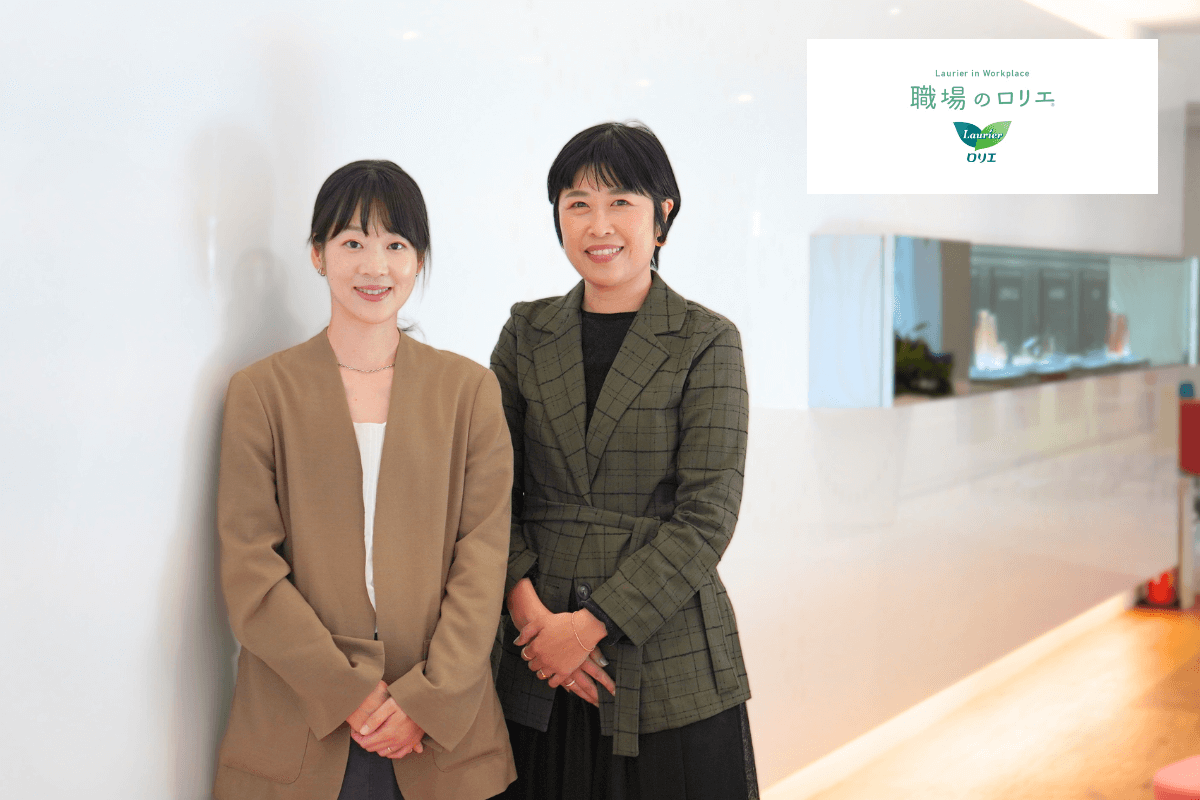
朝のバタバタ、仕事のプレッシャー、子供の発熱。毎日のように頭を悩ませる仕事と育児の両立。さらに生理が重なると「もう無理・・・! 」と思うこと、ありませんか?
実は、同じように悩む女性たちは想像以上に多く、働くひとたちの声から生まれたのが『職場のロリエ』です。誰でも使える生理用品が職場に常備されているだけで、どんな変化が起きるのか? なぜこの取り組みが必要だったのか?
今回は『職場のロリエ』の立ち上げから、マーケティング ・広告・クリエイティブに携わる花王株式会社(以下、花王)の手島佑梨さんと松永沙都子さんにお話を伺いました。
ライフステージの変化に合わせて柔軟にキャリアを築いてきたお二人が、どのような工夫をして家庭と仕事のバランスを取ってきたのか。さらに、その実体験が『職場のロリエ』にどう活かされ、働く女性たちの支えになっているのか。そのリアルなストーリーをお届けします。
(2025年1月取材)
目次
プロフィール紹介
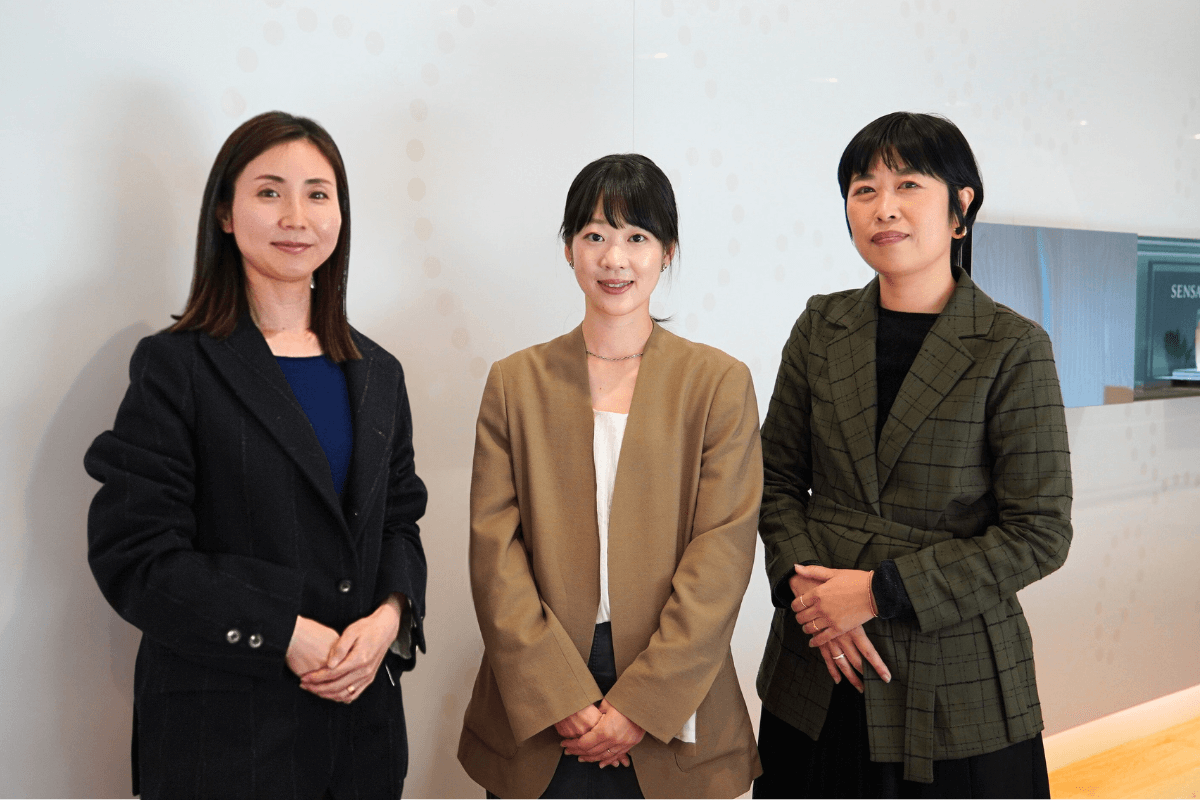
手島 佑梨 さん(写真中央)
花王株式会社
ハイジーンリビングケア事業部門 サニタリー事業部 マーケティング職/シニアマーケター
大学卒業後、花王に新卒入社。販売会社で企画営業・販売マーケティングを7年間経験後、本社異動。ホームケア事業部でバスマジックリン等を担当し、第1子の産育休を経てサニタリー事業部へ異動。『職場のロリエ』のマーケティングに携わり、一昨年シニアマーケターに昇格。2度の産休直前に大型新製品の発売や昇格など大事な局面を迎える中、しなやかにキャリアを築き、昨年春に復職。職種を超えた異動を重ね、新たな挑戦を続けている。
松永 沙都子 さん(写真右)
花王株式会社
作成センター 第1ブランドクリエイティブ部/クリエイティブディレクター
美大卒業後、デザイン制作会社を経て、2007年に花王のインハウスクリエイターとしてキャリア入社。TVCMやWEB動画を含むコミュニケーション全体の企画・プランニングに携わる。2度目の育休から復帰した2020年から『職場のロリエ』立ち上げメンバーとして 、生理用品ブランド『ロリエ』を担当し、2021年よりブランドリーダーに就任。2023年「JAAチャレンジアワード」金賞を受賞。生活者の声に寄り添い、心地よい日常を作るコミュニケーションを追求している。
山中 泰子(インタビュアー)(写真左)
株式会社QOOLキャリア 代表取締役社長
大手IT系人材サービス企業で人事として、採用・育成・制度設計等を経験。自治体とともにひとり親家庭の就業支援事業を立ち上げ、保育施設を併設した就業施設の開設・運営に携わる。その後、上場会社の人事担当執行役員、スタートアップ企業の人事責任者を経て、2022年4月からQOOLキャリアで代表に就任。1児の母である自らの経験も活かし、キャリアアドバイザーとして仕事と育児の両立に悩む女性のキャリア支援も行う。
「あの頃は大変だった…」仕事と家庭のバランスを見つけるまで
――初めての子育てと仕事の両立について、当時はどんなことを感じていましたか?
松永さん(以下、敬称略): 10年前に長男を出産した時は、時短勤務をしながら仕事と育児に追われる毎日でした。子育てしながら働く少し上の先輩たちは、どこか「すみません」と言いながら働いているような感じで、子育てとの両立が当たり前ではなかったですね。フレキシブルな働き方の選択肢も少なく、少し肩身の狭さを感じていました。
急な発熱やお迎えなどは日常茶飯事で、会社を休むしかない状況。仕事が滞ることや、メンバーに迷惑をかけることにストレスを感じていました。 花王に入社する前の制作会社は勤務時間が不規則で忙しく 、朝タクシーで帰るような生活をしていたので、子育て中の社員とそうでない社員のギャップも気になっていました。
山中: すごく共感します。私も当時は「子どもを産んだものの、周りと同じように働くしかない」という感覚がありました。
松永: 育休からの復職時、チームも仕事も働き方も変わってとても不安でしたし、気も張っていました。そんな中、同じチームの先輩が「限られた時間の中でどんな工夫ができるか」を一緒に考えてくれたんです。ただ仕事に戻るだけではなく、今までと同じようにはできない現実を受け止めた上で、どうすればパフォーマンスを維持できるのか、とことん話し合いました。「パフォーマンスを落とさない」という覚悟も持てましたね。そのやりとりが私のキャリアの大きな支えになっているので、とても大切な時間でした。
時短勤務だから仕方ない、という言い訳もできましたが、甘えたくなかったんです。仕事の満足度にも関わることなので、自分のためにも、良質なクリエイティブを世に届けるためにも、とにかく考え抜きました。
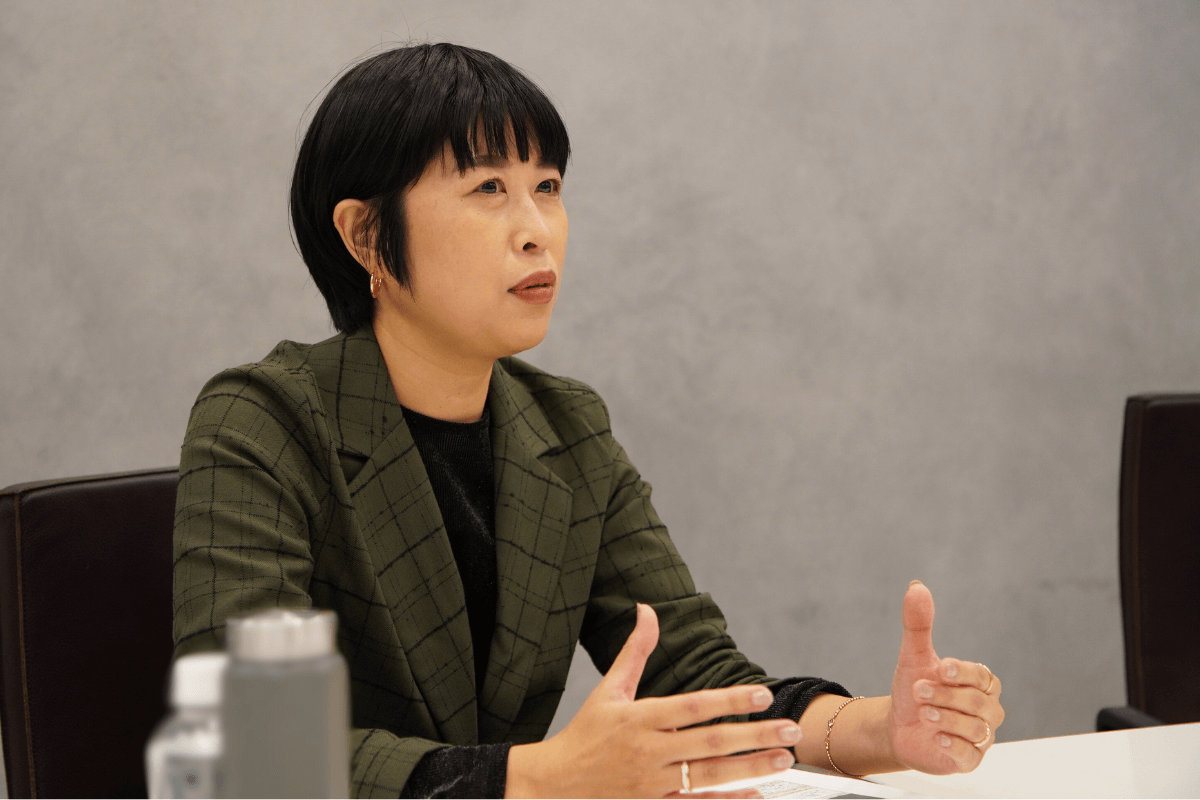
山中: 私自身も環境の変化に合わせて、譲れるものと譲れないものを整理してマネジメントすることは、ママになって得たスキルかもしれません。大変ですが、その分スキルアップしている実感もありますよね。
松永: 子どもが生まれる前と同じ働き方はできません。でも、変化を前提に話し合い、サポートしてもらえたことで乗り越えられました。今では私が後輩を同じように支えられるよう心がけています。
育休中に気づいた仕事への情熱
――育休中に感じたことや、復職への思いについて教えてください。
手島さん(以下、敬称略): 実は、長男と次男の妊娠中、割と出産予定日近くまで仕事を続けていました。幸い出産予定日通りに経過していたので、メンバーからは「まだいるけど、大丈夫?」と心配されることもありましたが(笑)、大型新製品の発売直前という大事な局面を迎えていたので、キャリアを続けるためにもしっかり向き合いたかったんです。会社としても前例の少ないケースでしたが、母子ともに健康で、希望通りに働き続けられたのは恵まれていたと思います。早く復職すること自体が楽しみで、フルタイム勤務を選択しました。フレックス制度を活用しながら、家庭と両立できそうと思えたことも1年待たずに復職を決める大きなポイントでしたね。
山中: それはとても新鮮な視点ですね。キャリア支援の現場では、復職後に転職を考える方の相談が多いので、「楽しみで復職する」というお話は驚きでした。復職を前向きに捉えられるのは素敵です。
手島: 育休中は家事のメインを担っていましたが、思っていた以上に大変だったことも、復職が楽しみになった理由かもしれません。気づかないうちに「家事・育児は女性がするもの」と思い込んでいましたね。頑張りすぎてしんどくなることもありましたが、週に1~2回でも夫が子どもの迎えを代わってくれるだけで本当に助かりました。
特に私の場合は、料理がどうしても苦手で。育休期間で得意にしたいと積極的に作り続けましたが、苦手なことは苦手だと認めることも大事だと気づきました。最初は「ちゃんとやらなきゃ」と気負っていましたが、無理に頑張るより、できることを工夫しながら進める方が大切だと実感したんです。結果的に「復職」を目標に育休期間を過ごせたことで前向きな気持ちになれましたね。
息子は2人とも生後8〜9カ月で保育園に預け始めたので、寂しい思いをさせているのではと悩むこともありました。その分、週末や長期休暇は家族との時間を大切にしています。仕事をすることで自分の世界も広がり、気持ちのリフレッシュにもなりますし、職場の同僚は友人のような存在。復職後は「おしゃべりをしに行く感覚」で働ける環境がありがたかったです。

『職場のロリエ』プロジェクトへの熱い思い
――お二人が関わる『職場のロリエ』誕生の背景と、どんなサポートを目指しているのか教えていただけますか?
松永: プロジェクトは2020年から始まりました。40年以上続く『ロリエ』ブランドのコミュニケーションを一度見直し 、単に商品の機能を伝えるだけにとどまらず、生理期に困る女性たちに実際に役立つサポートを何か実現できないか 。花王のロリエメンバー、代理店のプランナー、制作会社のプロデューサーといった多彩なメンバーが垣根を超えて、ゼロベースで熱い議論を重ねました。男性メンバーは打 ち合わせ後に自宅でご家族と話したリアルな意見を次の会議に持ち込むなど、フラットで率直な意見交換ができていたと感じます。2020年頃からのディスカッションの結果、2022年3月に『職場のロリエ』構想が形となり、約2年越しのプロジェクトとなりました。
山中: 2022年というと、コロナ禍でリモートワークが主流でしたが、プロジェクトにどのような影響があったのでしょうか?
松永: リモートワークに切り替わっていたので、職場でのナプキン交換に困るケースが減っている現実もありましたが、根本的な狙いは「働く女性のエンパワーメント」に変わりはありません。当初「オフィスロリエ」として進めていましたが、オフィスに限定されないよう、『職場のロリエ』とネーミングを変更したことが今振り返るとターニングポイントだったと思います。医療現場や建設現場、工場などオフィス以外で働くあらゆる職種の方々にも寄り添えるようになり、職場環境を変えていくきっかけとして提案ができるようになりました。
山中: 二階堂ふみさんのCMも印象的でしたね。ディレクションは松永さんがご担当されたのでしょうか?
松永: 二階堂さんの意識の高さには何度もハッとさせられました。「もっと男性にも知ってもらいたい」 という意見をもらい 彼女の存在がプロジェクトに大きな刺激を与えてくれました。
プロジェクトの立ち上げ期間は、次男の育休復帰から間もない頃でしたが、リモートワークを活用できたことで、通勤に時間を取られることなく仕事に没頭できたのがとてもありがたかったですね。
広告の枠を超え、誰かのためになるアクションを実現したいという思いが溢れ、最終の企画プレゼンで事業部長からOKが出た時の歓びは今も忘れられません。毎日、この活動が広がるたび、熱い想いが再燃しています。

手島: 私は『職場のロリエ』の導入が始まった段階でプロジェクトに参加しました。もちろん私の職場にも『職場のロリエ』があります。生理中に保育園の送迎や会議が詰まっている時など、ナプキンを買いに行く余裕がない時、お手洗いに設置された「職場のロリエ」を見るとホッとするんですよね。少しの安心感が働く環境の改善につながると実感しました。
松永: 生理の全てを詳しく知る必要はありませんが、最低限の症状や困りごとを把握するだけで、働く女性へのサポートや職場環境の改善につながると考えています。私自身、若い頃急な生理に焦ってコンビニに駆け込んだ経験があり、あの時『職場のロリエ』があったらどれほど助かったか、と思いますね。今も小学生になった長男を送り出してから次男を保育園に預けてそのまま出勤という日も多く、「しまった、ナプキンを入れ忘れた!」ということが。会社に行けばナプキンがあるから大丈夫という安心感は、思っていた以上に精神を安定させてくれるなと実感しています。
手島: 『職場のロリエ』は、女性だけでなく、誰もが安心して働ける環境づくりの一歩だと思うんです。ちょっとした配慮が、職場全体の思いやりや支え合いにつながることを願っています。
仕事も育児も無理しすぎない! 今だからできる工夫
――育児と仕事の両立を続ける中で、最初の頃と比べて感じ方に変化はありましたか? 今の働き方とあわせて教えてください。
松永: 今はフルタイムで、 基本は8時半から17時までですが、フレックスを活用して7時から20時の間で1日の勤務時間を調整しています。朝早くに始業して、中抜けして保育園に寄ってから出社するスタイルに落ち着き、出社は週に3~4日、リモートワークは毎日していますね。基本ワンオペ育児ですが、休むしか選べなかった過去に比べて、今は自分で調整できる余地があることで、心がとても軽くなりました。会社の制度には本当に感謝しています。
山中: フレックスやリモートワーク、チームの理解など、花王さんの風土や制度が支えになっているからこそ、2人子育てをしながらフルタイム勤務が実現できるんですね。
松永: とはいえ、子どもの体調不良は予測できないことも多くて、そのたびに調整が必要です。急な発熱時は、案外仕事から育児モードにパッと切り替えられるのですが、熱がおさまって元気に家にいるときのリモートワークが、実は地味にしんどいんです。元気な子どもが隣にいる状況で、打ち合わせをしたり、資料をつくったり、二足のわらじ状態で脳みそがフリーズしそうになりますね(笑)。最初は、同じ部屋にいる子どもではなくパソコンと向き合っている自分に後ろめたさを覚えることもありました。仕事に真剣に取り組む姿を見せるのも悪くないかも、と見方を変えて、自分が心地のいい方法を模索しながら、育児と仕事、どちらも大切にして、私なりに工夫しています。
山中: お忙しい毎日かと思うのですが、どんな工夫で乗り切っていますか?
松永: 毎日の時間を綿密に組みつつ、柔軟に調整しています。会社のスケジュール表には、仕事以外のToDoも書き込んで、優先順位をつけています。たとえば、「朝子どものお弁当をつくる」「PTAで昼休みに学校に寄る」などとても細かく入れていますね。次男が5歳になり、できることがぐっと増え、私が世話をしているというよりも仕事で眉間に寄ったシワを伸ばしてくれる存在になっています。子どもらしい言動に癒され、笑顔とパワーをもらい、そのエネルギーが仕事にもつながっていると感じます。
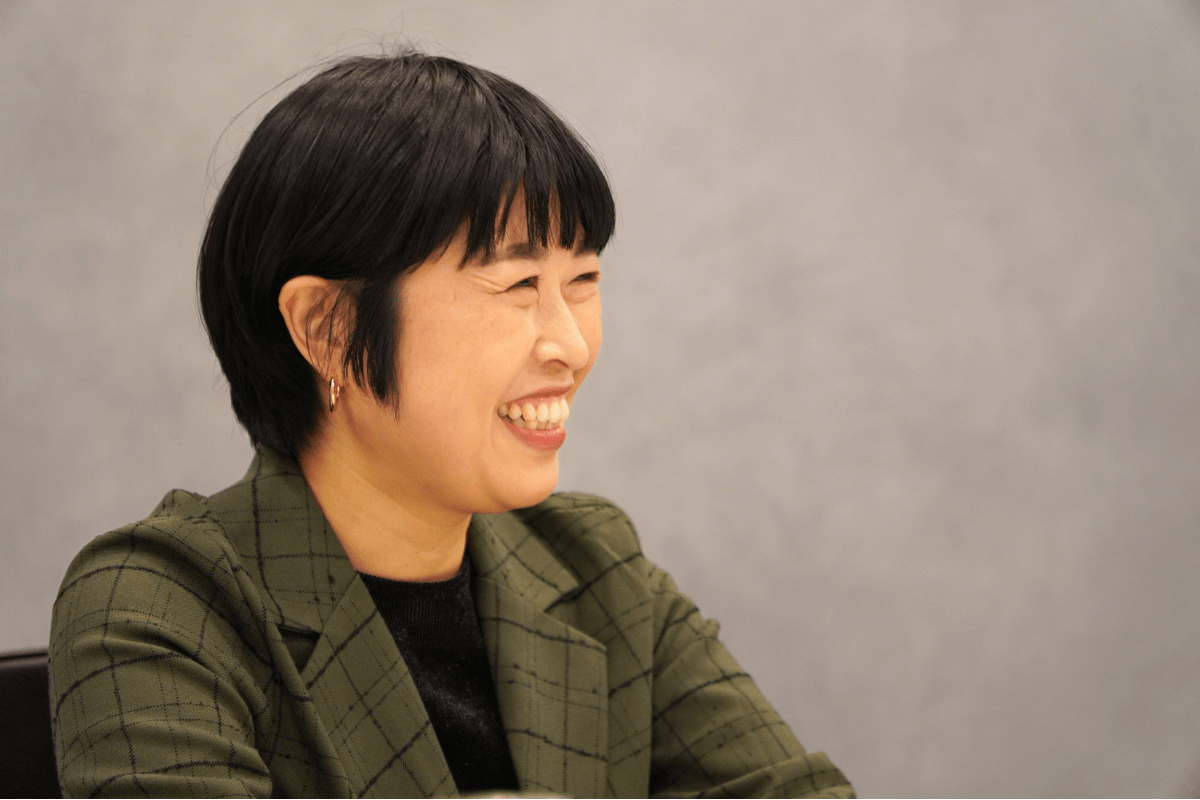
夫もワンオペ!? 共働きで支え合う家事・育児と仕事の両立
――昨年の春に復職されたばかりとのことですが、共働きで子育てをしながらのお仕事、どのように工夫して支え合っていますか?
手島: 仕事の予定は月ごとに立てて、夫と家事・育児の分担をしっかり決めています。例えば、私が早朝から仕事の日は夫が子どもの送迎を担当しますし、出張や重要な会議があるときは、1ヶ月前にはお互いに予定をすり合わせて、なるべく「外せない仕事の日」がぶつからないよう調整しています。
我が家では、家事・育児を担当する日は「完全ワンオペ制」。寝かしつけまでを担当するので、帰宅時間が20時ごろになりそうな日は、あえて仕事を続けて遅めに帰ることもあります。中途半端な時間に帰ると子どもが興奮してしまい、寝かしつけに1時間以上かかることもあるので、そこは割り切っています(笑)。
山中: ご夫婦での調整力がすごいですね! きっちり分担するって、意外と難しい気がします。つい手を出したくなったりしませんか?
手島: お互いの実家が遠く、シッターさんに頼む選択肢もなかったので、「どうにか2人で乗り切ろう」と試行錯誤した結果、このスタイルに落ち着きました。子どもたちも、私がいない日は夫との時間を楽しんでくれているようですし、お互いがそれぞれの役割を大事にできていると感じます。
最近では宿泊を伴う出張にも行けるようになり、本当にありがたいです。とはいえ、急なトラブルで仕事を休まざるを得ないこともあるので、普段から上司やチームメンバーには状況を共有し、助けてもらえる環境を整えています。チームが支えてくれるからこそ、無理なく仕事を続けられるんですよね。
先日、職場の家族同伴イベントに息子を連れて行ったのですが、それ以来、3歳の長男が「これママのお仕事のひとが作ったの?」と家の中で花王マークを見つけては聞いてくるようになりました。楽しそうに働く姿も、忙しく頑張っている姿も、子どもには見せていきたい、そう思いながら、これからも夫と支え合っていけたらと思っています。
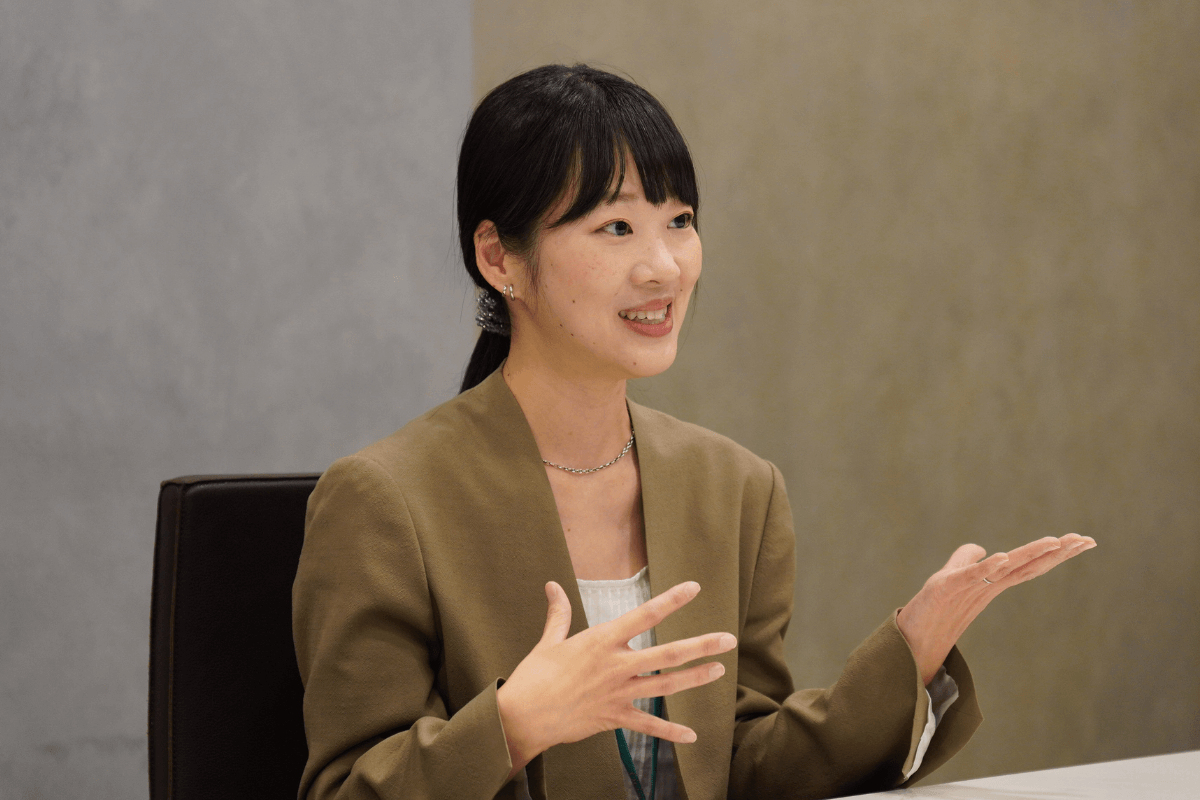
少しずつ進む、生理に対する意識の変化
――『職場のロリエ』の導入を通じて、企業内でどのような文化や雰囲気の変化が見られましたか?
手島: 『職場のロリエ』を導入いただいた企業の97%が継続を希望され、導入企業は350社を超えました。導入された企業様からは、「企業が率先してこうした取り組みを進めてくれることで、職場全体の雰囲気が変わる」「これまでなかった視点を持てるようになった」といったお声をいただき、職場環境の改善につながっていると実感しています。
山中: 導入企業が増えることで働く女性の健康や快適な職場環境について話しやすくなり、社会全体の理解が進んでいくのが嬉しいですよね。
私たちQOOLキャリアでも『職場のロリエ』を導入しましたが、実際に設置してみると、生理について「知っているつもりだったけど、知らなかったことが多い」と気づかされることがありました。導入時に視聴した研修動画では、経血の仕組みや痛みのメカニズムが図解でわかりやすく説明されていて、症状の個人差を理解することが大切だと改めて実感しました。特に、生理中のナプキン交換が難しい環境にある職場では、ナプキンがないことが「緊急事態」になり得ることを改めて認識しました。職場にナプキンが常備されていることで、女性社員がより安心して働ける環境になると感じています。

QOOLキャリアで導入された『職場のロリエ』設置風景
松永: 『職場のロリエ』を設置したことで、生理に関する理解が深まっただけでなく、体調管理全般について職場内での会話が増えたというお声も寄せられています。
他にも、研修動画を見た男性社員が「長時間の会議では意識的にトイレ休憩の時間を挟もう」と声をかけてくれるようになるなど、小さな気づきが職場環境の改善につながっているようです。
職場にナプキンが備品としてあることは、単に「生理用品が手に入る」という利便性だけでなく、「いざというときの安心感」につながると感じているようです。忙しい日々の中で、職場に必要なケアが備わっていることは、安心して仕事ができることへの助けになると思います。
山中: 『職場のロリエ』のように、必要なときに適切なケアを受けられる環境は、まさに多様な働き方を支える大切な取り組みですね。今回の導入を通じて、私自身も生理だけでなく、育児や介護、ヘルスリテラシー全般について、職場としてどのようなサポートが必要かを改めて考える機会になりました。
QOOLキャリアとしても、社員一人ひとりが健康と向き合いながら、より安心して働ける環境を整えていきたいと思います。
想いがつながる、広がる、働きやすい環境
――『職場のロリエ』の今後の展望や、実現したいことがあれば教えてください。
松永: おかげさまで、多くの方に共感いただいていますが、「導入したいけどハードルが」と悩まれる企業様も少なくありません。そんな企業様の背中を押せるように、『ロリエ』としてどんなサポートができるのか、一緒に考えていきたいですね。
10年後、「昔は会社にナプキン持って行ってたよね」なんて笑って話せる日がくるのが私の夢です。
今でも“生理は隠すもの”という空気はまだあります。でも、『職場のロリエ』があるだけで、ナプキンの交換時に音を気にするような無意識の気遣いから解放されて、生理の日ももっと自然に過ごせる。そんな小さな変化が、職場の居心地を大きく変えていくと思うんです。
「どうやって伝えるか」もすごく大事だと思っています。見た目のデザインや、職場で違和感なく馴染むパッケージ、気軽に手に取りやすい工夫など、ちょっとしたクリエイティブの力で「置いてみようかな」と思える雰囲気を作っていけるはず。『ロリエ』として、そんなコミュニケーションもどんどん考えていきたいです。
手島: 実は今、職場だけでなく学校への設置を目指す『学校のロリエ』プロジェクトも進めています。
私が初経教育を受けた頃は、小学校高学年の女子だけが体育館に集められて説明を受けるスタイルでした。でも今、幼い息子たちを育てる中で、「もっと早い段階で、男女一緒に生理について学べたら?」と考えるようになったんです。
生理が「特別なもの」ではなく、誰もが知っていて当たり前のことになれば、将来、働く環境もどんどん変わっていくはず。『ロリエ』としてできることを、これからもみんなで一緒に考えていきたいです。
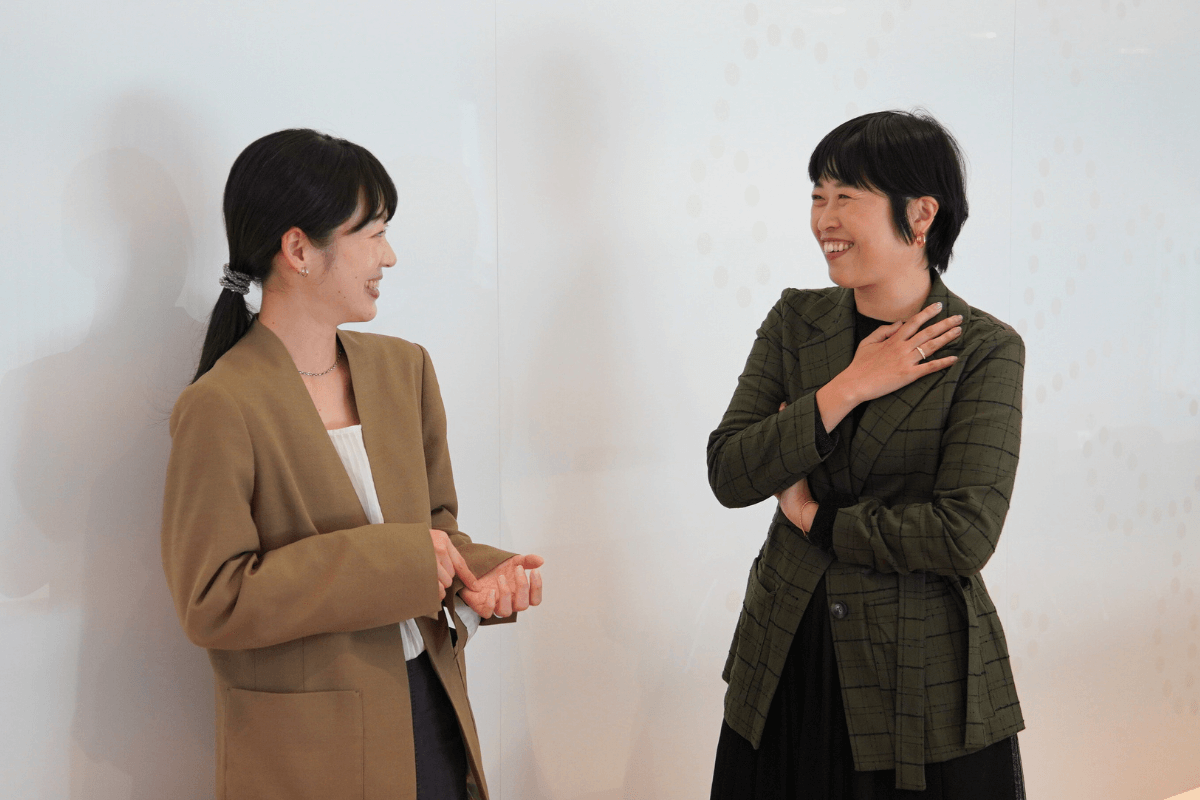
心配事は尽きないけれど、まずは自分を大切に
――子育てと仕事の両立に悩む方々に向けて、お二人の経験から「ちょっと心が軽くなるヒント」をいただけますか?
松永: 子育てと仕事を両立しなきゃ! と肩肘を張っていたのが10年前です。でも、振り返ると「両立」という考え方自体、私には合ってなかったんですよね。やることが増えて大変だと思い込んでいたけれど、子どもが成長すれば環境も変わるし「こうしなきゃ」と決めつけずに、もっと柔軟に考えてよかったのかもと思います。
今では「両立」ではなく「バランスを取る」と考えるようになりました。「子育て」と「仕事」、2つを別々にこなすのではなく、1つの流れの中でどう組み合わせるかを考えるのも大事かなと思います。1人しかいない自分が、どうやったら無理なく楽しくできるか。その視点を持つと、少し気持ちがラクになるかもしれません。
職場の環境って不思議で、ほんの少しの工夫や誰かのひと言で変わりますよね。『職場のロリエ』の小さな変化から働きやすい流れが生まれたら素敵だなと思います。
毎日を無理せず。私の経験が、みなさんご自身のスタイルに合う工夫のヒントになったら嬉しいです。
手島: 正解がないからこそ、悩みますよね。家庭環境もサポートの形も住んでいる場所も人それぞれ。でも、試行錯誤を繰り返すうちに自分のスタイルが見つかっていくものだと思います。
私も、苦手なことを無理に頑張っていた時期がありましたが、それを乗り越えたからこそ、今は少しずつ自分らしいスタイルに近づいている気がします。一番大切なのは、まず自分自身を大事にすること。健康が一番です。そして、お子さんとの時間を優先することも、仕事に打ち込んでイキイキすることも、どちらも正解だと思います。定期的に働くスケジュールを見直したり、自治体の子育てサポートを活用したり、できることから試してみてください。
職場の皆さんには、子育て中のメンバーが忙しさや不安を感じるとき、温かく見守っていただけると心強いです。『職場のロリエ』のようなちょっとした気遣いが、働きやすい環境につながることもあります。先輩の経験談や励ましのひと言が、誰かの支えになるかもしれません。そんな温かいサポートが広がると嬉しいです。
ナプキンの備品化プロジェクト『職場のロリエ』
『職場のロリエ』は働く女性の悩みから始まったプロジェクトです。
賛同企業と共に育てていく活動として職場環境を変えていく取り組みを続けています。
現在マーケティング部門から男女の若手社員が中心となり、社内でアンバサダーを募ったり、イベントへ積極的に出展したり、日々「働くひと」の環境をよくする思いで活動されています。
詳しくはこちら:https://www.kao.co.jp/laurier/project/shokuba/
ライフステージに合わせたサポートができる福利厚生「TUMUGU(ツムグ)」
働きがいをアップデートする福利厚生サービス「TUMUGU(ツムグ)」では、LINE完結の個別専門家相談、ヘルスリテラシー向上セミナーを提供しています。
両立支援のための仕組みや、社員がライフステージに合わせて柔軟に働けるサポートを提供。企業の成長と従業員のワークライフバランスを両立させ、ライフステージの変化に寄り添いながら長期的な活躍を促進します。
詳しくはこちら:https://tumugu-service.jp/
お問い合わせはこちら:https://career.qo-ol.jp/tumugu/